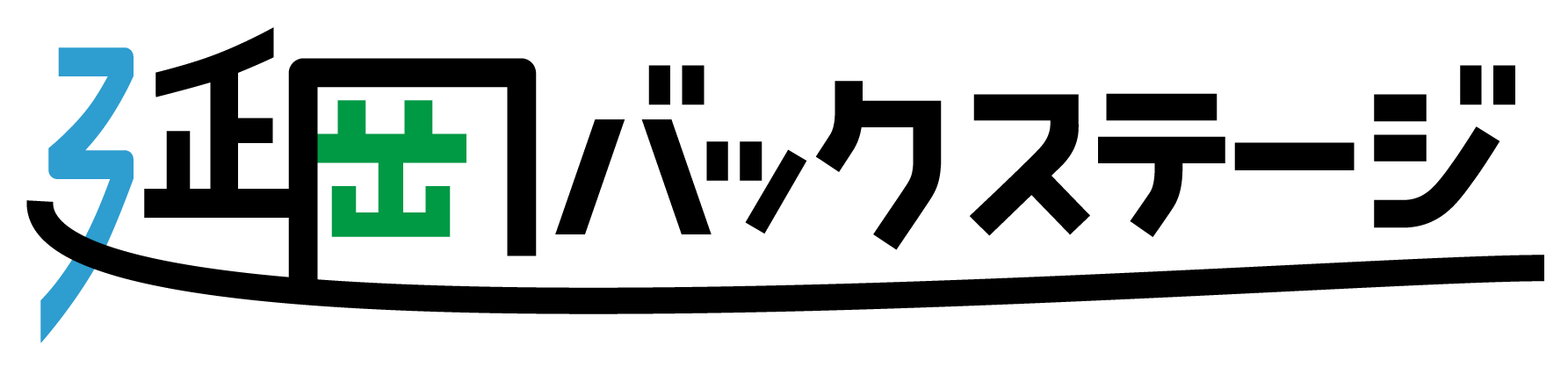3年ぶりに通常スケジュールの6月開催となった、今年のトニー賞でもBLM運動を受けての一連の動きは顕著だった。
今年のトニー賞で、新作ミュージカルとしては最多となる4部門に輝いたのは、歌手の故マイケル・ジャクソンの半生を彼のヒット曲により紡いでいく『MJ』。

Photo:Emilio Madrid
莫大な製作費が投じられ彼の世界観が再現された同作品は、当初ブロードウェイで2020年の夏に開幕する予定だったが、パンデミックによりブロードウェイが閉鎖、棚上げとなってしまった。

マイケル・ジャクソンのシンボルでもあるムーンウォークのシルエットが目を引く看板が劇場に掲げられたまま、1年半以上の月日が経過することとなるが、その間に人種平等に対する意識の変化が起こる。
アフリカ系アメリカ人として人種差別とも戦った伝説の歌手の物語が、これまで以上に重みを増していったのである。
トニー賞では作品賞こそ逃すが、マイケル・ジャクソンを演じた若干22歳の新人が主要部門のひとつであるミュージカル主演男優賞にサプライズで輝く。
壇上でトロフィを掲げた彼は、マイクに向かってアフリカ系アメリカ人の子どもたちに語りかけ、たとえ家族に恵まれていなくても、夢をかなえることは可能なのだと諭し、黒人同士が支え合っていることを強調、時世を意識したスピーチで希望を与えたのだ。
全26部門から成るトニー賞だが、最も注目を集めるのは自ずとミュージカル作品賞。
今年は同部門で候補に挙げられた半数以上の作品に、何らかの形でアフリカ系アメリカ人の苦難を描いた内容が織り込まれたのは、演劇界の関心事が反映された結果に他ならない。
そして、賞レースを制したのも、その作品の中のミュージカル『ア・ストレンジ・ループ』。

Photo:Marc J. Franklin
現代のニューヨークを舞台に、ブロードウェイの劇場で案内係として働いて日銭を稼ぐ、アフリカ系アメリカ人のゲイの青年を描いた作品だ。
ミュージカル作家を目指す主人公の青年は様々なコンプレックスを抱えている。
肥満で、下半身に自信が持てず、肌の色が周りのアフリカ系アメリカ人よりも黒く、同性愛者であることや黒人としてのアイデンティティが欠如していることを両親から咎められるなど、悩みの種は尽きない。
彼はそんな自分自身についての全てを、包み隠さず曝け出すミュージカル作品を創ろうと葛藤し、自問自答を繰り返す。
自分自身の分身でもある6人の心の声と対峙し、生み出す自伝的な作品の方向性を想い描こうと奮闘するのだ。同ミュージカルは、すでに2020年にピューリッツアー賞を受賞しており、トニー賞での作品賞獲得は番狂わせのない結果となった。
6月のトニー賞授賞式をもってブロードウェイはシーズンを締めくくり、今度はオフ・ブロードウェイの小劇場で様々な舞台が幕を開けるニューヨーク演劇界の夏が本格化する。
感染対策の規制が緩和され、観客にワクチン接種証明の提示が求められなくなり、マスク着用義務の撤廃も進むニューヨーク演劇界が迎えるパンデミック前の状態に近い久々の夏で、最初に注目を集めたのも、アフリカ系アメリカ人の一家を描いた作品だ。
数々のヒット作をブロードウェイに送り込んできた名門のオフ・ブロードウェイの劇場で、期間限定の公演を幾度となく延長するほどの人気を誇るのは新作ストレートプレイの『ファット・ハム』。

Photo:Joan Marcus
シェイクスピアによる四大悲劇の代表作『ハムレット』を現代のアフリカ系アメリカ人の家庭に置き換えた戯曲だ。父親を殺した叔父への主人公の復讐劇という大筋は下敷きとなるシェイクスピアの悲劇と同じ。
しかし、『ファット・ハム』の主人公は、生き方が不器用なゲイで肥満の黒人青年となり、舞台は彼の母親と叔父との結婚パーティーが行われている家の裏庭だ。悲劇でありながらも随所に笑いが散りばめられ、5月に今年のピューリッツアー賞の演劇部門を受賞し脚光を浴びた。
さらには、同じくピューリッツアー賞を獲得し、トニー賞を受賞したばかりのミュージカル『ア・ストレンジ・ループ』と限りなく主人公の設定が似ているという偶然も関心を集め、チケット入手が困難を極めるようになり、夏一番のヒット作となったのだ。
2018年~2019年のリサーチ結果によると、1年を通してのブロードウェイ全体の観客の数は過去最高となる1480万人に上ったという。
その中で白人以外の観客が占める割合は300万人に留まったとデータは示す。この数字から推測する限り、人種マイノリティについての題材を取り上げて、彼らをターゲットにした作品を上演しても、そこまでの需要が見込めないという現実も垣間見える。
ブロードウェイの閉鎖が解除されてから流行した、アフリカ系アメリカ人にスポットを当てる多数の作品だが、どれもメディアから軒並み無条件で高い評価を得てきた。
その一方で、同じ類の作品同士で過当競争が起こり、そろって集客に苦戦を強いられ、共倒れになるという事態もこの1年の間に発生した。
こうした流れを受け、人種差別の排除に対する使命感が先走りし、本質が見落とされていくのではないかと、暗に疑問視する報道があるのも事実。
パンデミックを経て生まれ変わった新時代のニューヨーク演劇界が、はたして今後どう人種問題という社会の動きと向き合っていくのか、議論は続く。

Photo:Emilio Madrid